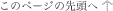明治36年(1903)に開催された第五内国勧業博覧会の跡地に、明治42年(1909)再開発のプロジェクトが立ち上
がり、「新世界」は、一大歓楽街の賑わいを見せるようになります。
その賑わいのひとつに、大阪大相撲がありました。
初代朝日劇場の経営者、「朝日山」の名代である十二代朝日山四郎右衛門は新世界に、四股名にちなんだ
「朝日劇場」を建設、自らその経営にあたります。
初代朝日劇場は洋風劇場建築です。
関西新派劇の秋月司櫻、後の日活大将軍時代の時代劇役者喜多次郎らが新派劇を上演していました。
関西新派劇は当初は、劇団新派からの分派というイメージが強かったのですが、朝日劇場が開場する頃に
は、単に、「新派の系統の芝居を関西で上演する劇団」へと変わっていったようです。
朝日劇場は関西新派、新世界に新派を持ってくることで、千日前やキタ、さらに銀座や浅草に対抗しようと
した朝日山の心意気がうかがい知れます。
初代通天閣の開場より早い、明治43年(1910)のことでした。
しかし、朝日劇場の経営は、大阪相撲の衰退に伴ない、相撲協会からの批判の声も上がり朝日山の経営は僅
か2年と長く続きませんでした。
その後、明治45年(1912)二代目経営者となった橋本繁太郎が「朝日劇場」を受け継ぎます。
当時売り出しの興行師橋本繁太郎は、兵庫県川辺郡丸橋(現在の宝塚市)の出身で大工から身を起こします。
明治末から大正にかけての大阪興行界で活躍、朝日山のタニマチの一人であったと推測します。その大工の
頭が興行に関心を持つようになっても不思議ではありません。「池田の大工で終わるより、一旗上げて、一
角の男になりたい」という気概もあったと思われます。
繁太郎が大阪に向かい、新世界を本拠地とするようになったのは、明治30年後半から40年代初めと思われま
す。興行に関わるようになった繁太郎は、周囲から押し出されるような形で地元興行界の実力者となり
ます。劇場譲渡の相談を持ちかけられる程になったのは自然な成り行きと見るべきです。
繁太郎は、晩年には、興行界のみならず、新世界全体の重要人物として知られるようになりました。詳細は
「新世界興隆史」に記されています。併せて、繁太郎は隣接する恵美須館の経営も引き継ぎます。
「朝日劇場」からは、曾我廼家鶴蝶(そがのやつるちょう)、宮城まり子、ミヤコ蝶々、藤山寛美、ディック
ミネなど多くの一世を風靡した人気の役者が巣立っています。
そして、現在も大衆演劇の殿堂として年間12の人気劇団が月替りで興行し、多彩な演目で多くのファンを楽
しませています。
場内は花道を挟んでお客様と役者が接近できる桟敷席と椅子席があります。
開場から100年以上続く「朝日劇場」は、これからも大衆演劇の魅力を伝えて続けてまいります。
大阪新世界で100年
社史